今回の症例は、再根管治療のケース。
患者さんは20代男性。
主訴は「歯茎から膿が出る。1−2年前に他院にて根管治療を行い、セラミッククラウンを入れている。状態をみてほしい。」ということだった。
口腔内を見ると、頬側にフィステルがある。
打診(+)、咬合痛(+)、頬側歯肉の圧痛(+)
フィステルに造影材(ガッタパーチャポイント)を入れて、レントゲン撮影した。
(術前のレントゲン、CT)

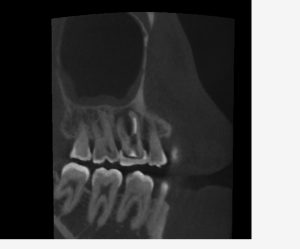
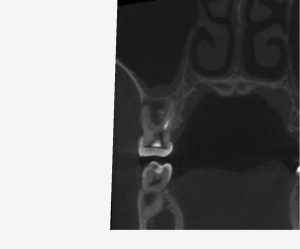
3根全てに根尖病変がある。
そして、分岐部に大きな穿孔(パーフォレーション)があった。穿孔部にも骨吸収を認める。
患者さんからの話を聞くと、どうやら前回の治療は抜髄だったようだ。
穿孔(パーフォレーション)とは、根管治療の最中に間違った方向に歯を削り過ぎてしまい、歯に人工的な穴を開けてしまうことをいう。
この部位に細菌が感染してしまうと、治療が複雑化する。
この根管治療の状態でセラミッククラウンを入れるのは、流石に無責任な治療であると言わざるを得ない。
患者さんが気の毒である。
推奨される治療は、再根管治療だ。
穿孔部の修復も行わなければならない。
(治療直後のレントゲン)

MB根、DB根はやや湾曲していた。
穿孔部に関しては、バイオセラミックパテにて修復。
治療は一回法で終了した。
幸い術後2週間でフィステルは消失した。
その後およそ1年間、仮歯の状態で経過経過を見ることとなった。
(術後1年のレントゲン、CT)


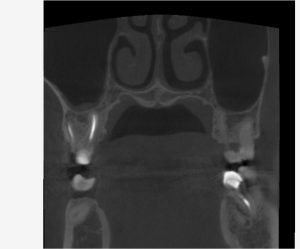
術後1年では一切の症状はなくなっていた。
根尖病変および穿孔部に関しても骨が再生しており、治癒が確認できた。
この後、最終補綴に移行した。
何とか歯を残すことができ、患者さんも喜んでおられた。
穿孔に関しては、現代の材料を使用すれば、良好な封鎖・修復が可能であることがわかっている。
本来、抜髄治療(初めて神経を取る治療)であれば、90%以上という高い成功率を誇るはずだ。
根管治療は術者の知識・技量・経験によって、その結果が大きく影響を受けやすい治療と言える。
治療を受ける際には、根管治療を得意とする医院を受診することをお勧めしておく。